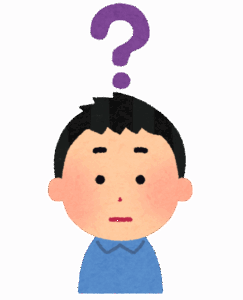
赤ちゃんが生まれたらどんな手続きをすればいいの?
種類や手続きの方法を知りたい。
こんな疑問を解決します。
赤ちゃんが生まれたら役所、職場、病院などに届出をしたり、お金を受け取るための手続きをする必要があります。
日頃やったことのない手続きは面倒だし、漏れがないか不安ですよね。
そこで、産後に必要になる手続き一覧をわかりやすくまとめました。
「産後にこういう手続きが必要になるんだな」と頭に入れておくと、事前準備がスムーズになって、バタバタせずに対応できますよ。
この記事を書いている人
びーた:元公務員、妻が助産師
妻(助産師、助産院で産後ケアなどママたちのサポートに奮闘中)
産後の届出手続き一覧
出生届出・出生証明書

出生届とは、生まれてきた赤ちゃんの氏名などを戸籍に記載するための手続きです。
戸籍に記載されることで、赤ちゃんの親族関係が公的に証明され、住民票などに記載されます。
届出書は、A3サイズの用紙に出生届と出生証明書が合わせて印刷されています。
出生証明書は、病院の医師等が記入する欄がありますので、産後退院するときに出生証明書に記入された届出用紙をもらうのが一般的ですね。
| いつまで | 出生から14日以内 |
| どこに | 子の出生地・本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役所 |
| だれが | 父または母 (婚姻関係にない子の場合は母のみ) |
| 持参物 | ・出生届及び出生証明書 ・母子健康手帳 ・印鑑(自治体によっては不要) ・身分証明書 |
| 注意点 | ・出生証明書欄に医師等が記入していること ・マイナンバーカードを持っている場合、オンライン申請できる自治体あり |
児童手当
児童手当とは、児童(0歳から18歳)を養育している家庭に支給される手当です。
児童の年齢や家庭の子どもの人数によって、手当の額が変わります。
令和6年10月から制度が変わりました。国の政策などの関係で、今後も変わるかもしれません。
【児童手当の支給額】
| 児童の年齢 | 児童手当の額 (1人当たり月額) |
| 3歳未満 | 15,000円 (第3子以降は30,000円) |
| 3歳以上高校生年代まで | 10,000円 (第3子以降は30,000円) |
| いつまで | 出生日の翌日から15日以内 ※申請した翌月分から対象となる 申請が遅れた月分は受け取れないので注意 |
| どこに | お住まいの市区町村役所 (公務員の場合は職場) |
| だれが | 父または母 ※原則生計中心者(所得の高い方)が受給者となる |
| 持参物 | ・児童手当認定請求書(役所でもらう) ・受給者の銀行預金口座情報がわかるもの ・受給者及び配偶者のマイナンバーカード(個人番号通知カードと本人確認書類) |
| 注意点 | ・母親の里帰り先(住民票のない自治体)での申請はできない ・振込先の銀行口座は、受給者本人が原則(妻や子の名義はできない) |
健康保険証
健康保険証は、子どもが医療機関を受診する際に必要になります。
退院した後も、定期健診や体調が悪くなって病院に行くことがあります。
手続きをしていないと、医療費が自己負担になってしまうため、早めに手続きをしましょう。
| いつまで | 出生後なるべく早く ※赤ちゃんの1か月健診で必要になる |
| どこに | 社会保険(会社員・公務員)の場合 →勤務先 国民健康保険(自営業)の場合 →お住まいの市区町村の役所 |
| だれが | 父または母 ※原則生計中心者(所得の高い方)の扶養に入る |
| 持参物 | 社会保険の場合 ・申請書(勤務先からもらう) ・マイナンバーがわかるもの ・その他勤務先に確認する 国民健康保険の場合 ・申請者の保険証 ・印鑑(自治体によっては不要) ・マイナンバーがわかるもの |
子ども医療費助成
子ども医療費助成制度は、入院や保険診療内の自己負担額を自治体が助成する制度です。
住んでいる自治体によって、子どもの対象年齢(0歳~中学生までなど)や助成額が異なりますので、ホームページなどで確認してください。
病院で医療証を提示すると、医療費が無料になるか一部減額されます。
| いつまで | 出生後なるべく早く ※赤ちゃんの1か月健診で必要になる |
| どこに | 社会保険(会社員・公務員)の場合 →勤務先 国民健康保険(自営業)の場合 →お住まいの市区町村の役所 |
| だれが | 父または母 ※原則生計中心者(所得の高い方)の扶養に入る |
| 持参物 | 社会保険の場合 ・申請書(勤務先からもらう) ・マイナンバーがわかるもの ・その他勤務先に確認する 国民健康保険の場合 ・申請者の保険証 ・印鑑(自治体によっては不要) ・マイナンバーがわかるもの |

小さいときはよく発熱や体の不調で病院にかかるので、この助成制度は本当にありがたいです。
出産育児一時金
出産育児一時金は、加入している健康保険組合から出産費用を受け取れる助成金です。
健康保険に加入していれば50万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関では48.8万円) が支給されます。※今後変動する可能性があります。
支払い方法は、次の3つに分かれていて、いずれかを選択します。
【支払い方法の種類】
| 種類 | 内容 |
| ①直接支払制度 | 出産に係る費用を病院が健康組合に申請し、直接支払われる。 退院時に差額分(自己負担分)のみ支払う ※多くの病院がこの方法で支払える |
| ②受取代理制度 | 出産する病院が①直接支払制度を利用できない場合に使用する 本人が健康組合に事前に申請しておき、健康組合からの支払いを病院が代理で受け取る |
| ③本人申請 | 出産費用全額をいったん本人が病院へ支払った後、健康保険組合に申請して支給してもらう ※病院へクレジットカードで支払い、ポイントを貯めるために選択する人もいる |
| いつまで | ①直接支払制度 →入院前または入院中 ②受取代理制度 →出産予定日の1~2か月前 ③本人申請 →出産翌日から2年以内 |
| どこに | ①直接支払制度 →病院から支払業務委託契約書などの書類を受け取って署名後、病院へ提出 ②受取代理制度 →申請書を病院に記載してもらい、健康保険組合へ提出 ③本人申請 →健康保険組合へ申請書を提出 ※国民健康保険の場合は市区町村 |
| だれが | 父または母 |
| 持参物 | ①直接支払制度 →直接支払制度の合意書または契約書、健康保険証 ②受取代理制度 →健康組合に提出する申請書、振込先口座がわかるもの ③本人申請 →健康組合に提出する申請書、出産費用が記載された領収書等、振込先口座がわかるもの |
出産手当金
出産手当金は、産休中のママの無給期間の生活費をサポートする助成で、加入している健康保険組合から支給されます。
支給対象期間は、産前6週間(42日)、産後8週間(56日)になります。
支給額は、産休中のママの標準報酬日額(勤務先の給与等で算定される)の3分の2×支給対象期間になります。
| いつまで | 産休開始日の翌日~2年以内 産前・産後に分けて申請も可能だが、産後にまとめて申請する人が多い |
| どこに | 勤務先 (勤務先から健康保険組合へ) |
| だれが | 母 |
| 持参物 | 出産手当金支給申請書(勤務先からもらう) ※病院の医師等に記載してもらう欄あり |
| 注意点 | 出産を機に会社等を退職していても、退職日までに1年以上継続して保険に加入しているなど、条件を満たせば受給できる可能性あり |
まとめ: パパが積極的に手続きしていこう
産後の手続き一覧について記載しました。
手続き関係は、理解しないといけないことや確認することが多くて、とても面倒ですよね。
でも、産前・産後のママにその負担をかけないようにするのがパパの役目のひとつ。
パパが積極的に手続き関係を進めてくれると、ママもとってもありがたいと思います。
ママの負担を減らして、ママの笑顔を増やしましょう!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

