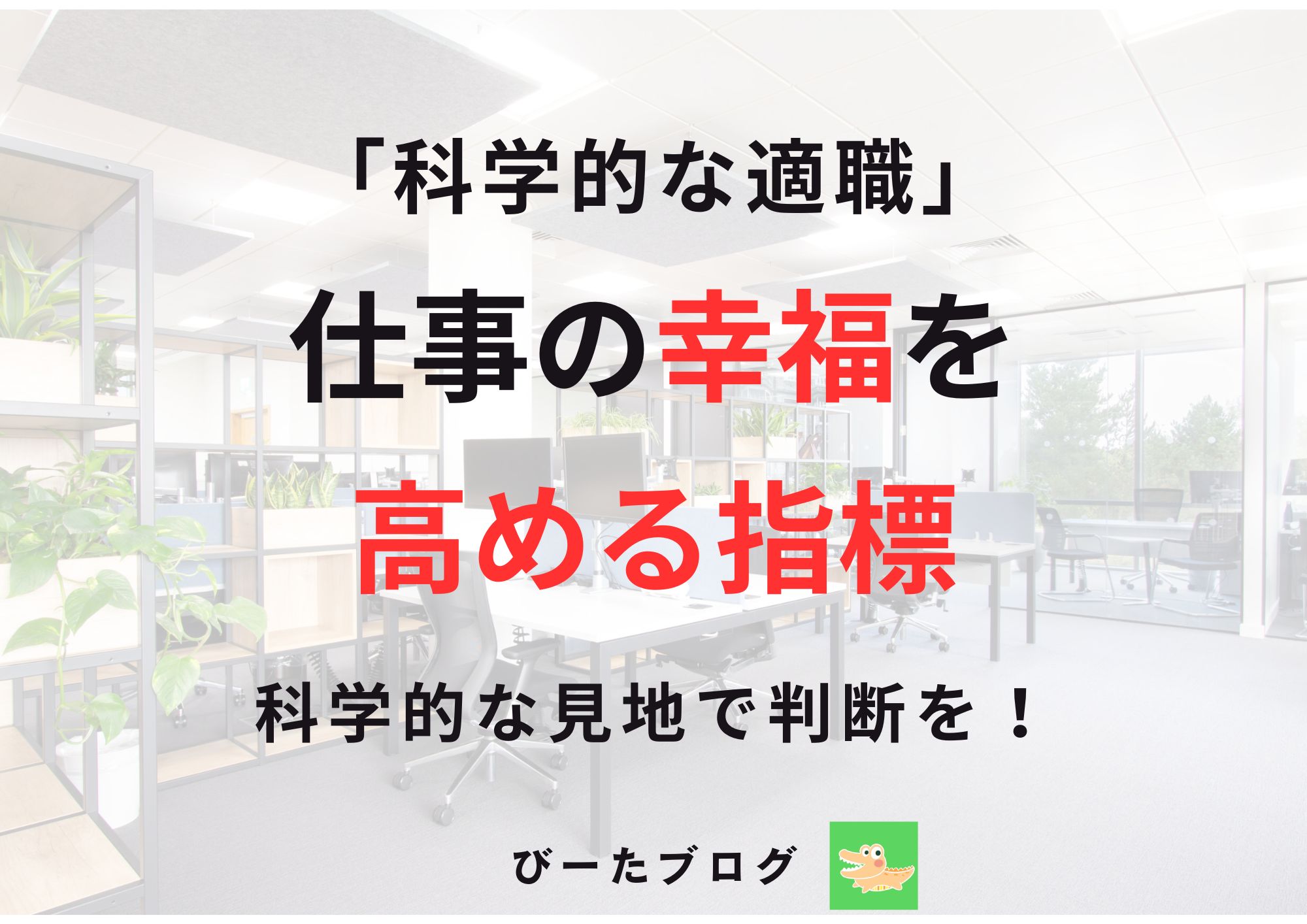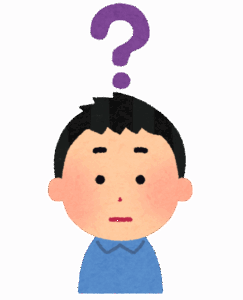
転職について考えているけど、そもそも幸福を感じる職場ってどんな条件なの?
逆に不幸になるのは?
仕事選びの参考にしたいな。
こんな気持ちの方に記事を書きました。
どういう仕事・職場なら幸せを感じることができるのか。
なんとなく思い浮かぶものはあるけど、曖昧な部分もありませんか?
また、不幸を感じる場合も同様です。
この記事では、このようなの疑問について、わかりやすく科学的な根拠で説明してくれている「科学的な適職(著者:鈴木 祐)」の内容をまとめました。
この本のすごいところは、適職選びの判断基準を世界の研究結果に基づいて明確に説明してくれている点です。
- 転職先を検討するとき
- 今の仕事・職場の状況を再確認したいとき
この記事を読んで、幸せになるための仕事選びのヒントにしていただけるとうれしいです。
さっそく見ていきましょう。
仕事の幸福度を高める指標7選

仕事選びでは、「この仕事がよさそう」という決めつけから入ってしまい、視野が狭くなりがちです。
そんな視野狭窄に陥らないためには、仕事の幸福度を高める要素を把握すべきです。
著者が挙げている具体的な要素は以下のとおり。
- 自由
- 達成
- 焦点
- 明確
- 多様
- 仲間
- 貢献
それぞれ解説します。
自由
1つ目は自由(裁量の大きさ)があることです。
仕事に関して、いかに自分の意思でコントロールできるかが幸福度に大きな影響を及ぼします。
- スケジュールを自分で設定できる
- タスクを選択できる
- 自由に意見が言える
- 勤務時間・場所を選択できる
これらの自由度が高いほど、幸福を感じやすいです。
とはいえ、顧客のために動いたり、組織の制約のもとで働くので、完全な自由は不可能ですよね。
ですが、
- 労働時間はどこまで好きに選べるのか
- 仕事のペースはどこまで個人の裁量にゆだねられるか
この2点は、仕事を選ぶ際の大きなポイントと認識するべきです。
達成
2つ目は、達成感を得られる環境であることです。
人間のモチベーションを高める最大の要素は、「少しでも仕事が前に進んでいるとき」ということが多くの研究で判明しています。
皆さんもこれまでの経験で実感していますよね。
- 計画に沿って、日々のタスクをこなす
- 重大なイベントの本番を乗り越える
目的に向かってプロジェクトを進め、達成した時は大きなやりがいを感じます。
達成のレベルが小さくても、コツコツ達成することでモチベーションを維持できますよね。
仕事選びで押さえておきたいポイントは、以下の2つです。
- 仕事のフィードバックはどのように得られるか
- 仕事の成果とフィードバックが切り離されていないか

公務員はこのフィードバック(住民の感謝、給与への反映)を感じづらい部分がありますね。
焦点
3つ目は、自分のモチベーションタイプに仕事内容が合っているかどうかです。
確度の高い性格テストに「制御焦点」というものがあり、人間のパーソナリティを攻撃型と防御型の2タイプに分けることができます。
- 攻撃型:目標を達成して得られる利益に焦点を当てて働くタイプ
- 防御型:目標を「責任」の一種と捉え、競争に負けないために働くタイプ
たいていの人はどちらかに分類され、焦点タイプに合った働き方をした方が、能力を発揮しやすく満足度も高まります。
あなたはどちらのタイプでしょうか。
タイプ別の仕事選びのポイントは以下のとおり。
- 攻撃型:成長を実感しやすい仕事
- 防御型:安心感と安定感を実感しやすい仕事

攻撃型タイプの人は、公務員の仕事はつらく感じやすいかも…。
明確
4つ目は、信賞必罰とタスクの明確さです。
信賞必罰とは、功績があれば評価され、過ちがあれば罰せられることですね。
評価や罰則の基準が明確であれば、モチベーションや行動に影響します。
タスクの明確さとは、例えば以下のようなものが明確な状態です。
- 組織の価値観やビジョン
- 現在の業務の意味(貢献)
- 上司の指示
上司の指示があいまいだったり、直属の上司とその上の上司の指示内容が違うような環境は、大きなストレスを感じます。
仕事選びでのポイントは以下の4つ。
- 組織に明確なビジョンがあるか
- ビジョンを実現するために、どのような工夫をしているか
- 人事評価はどのようにされるか
- 個人の貢献と失敗を明確に判断できる仕組みがあるか

明確なビジョンがあれば、判断する時間も省略できますね。
多様
5つ目は、業務の多様性です。
人間はどのような変化にもすぐに慣れてしまう性質があります。
得意な業務はラクで快適ですが、それだけをひたすら毎日続けることを想像してみてください。
かなりしんどいことがイメージできますよね。
- 自分の持ついろんなスキルや能力を幅広く活かすことができる
- 業務の内容がバラエティに富んでいる
という条件が幸福度を高めてくれます。
仕事選びでのポイントは2つ。
- 自分のスキルを使って多様な仕事ができるか
- プロジェクトの川上から川下まで関与できるか
仲間
6つ目は、職場の仲間・友人の存在です。
職場の人間関係が、大事なのは言うまでもありませんね。
アメリカの大規模な調査では、給料や仕事の楽しさと関係なく、社内に良い友人がいるだけでも幸福になることが明らかになっています。
逆に、人間関係の悪化は、長時間労働や福利厚生の不足の影響を上回る悪影響が生じることに。
仕事選びでのポイントは、
- 組織に、自分に似た人がどれくらいいそうか
が重要な視点になります。
「類似性効果」という心理現象で、人間は自分に似た人を好きになりやすいという特徴があるからですね。
価値観や考えが合う人の方が、良好な人間関係を構築しやすいです。
貢献
最後の7つ目は、貢献です。
わかりやすく言うと、「自分の仕事が誰かの役に立った」ことを感じやすいかどうかですね。
人のためにすることが、幸福度を上げることは様々な調査で実証されています。
幸福度が上がる理由は、以下の欲求が満たされるから。
- 自尊心:人の役にたつ→自分は有能だと思える
- 親密感:他人と親密になり、孤独感から逃れやすい
- 自律性:他人の指示でなく、自分で幸せを選択できたと感じる
犯罪に加担するような仕事をするのでなければ、社会に役に立たない仕事は基本的にありません。
が、自分の仕事が他人に貢献していると感じられた方が、幸福感にとっては有利です。
不幸に感じる職場の害悪

仕事の幸福度を高める指標を見てきました。
しかし、人間の心はポジティブ要素よりネガティブ要素の方が、圧倒的に影響力が大きいのだそうです。
いくら多くのポジティブ要素がそろっていても、ネガティブ要素1つで不幸に感じてしまうくらい強力です。
続いては、不幸に感じやすい要素を見ていきます。
大きく分けると以下の2つです。
- 時間の乱れ
- 職務の乱れ
詳しく解説します。
時間の乱れ
時間の乱れとは、仕事に関する時間が乱れたり、キャパを超えることによって悪影響を及ぼすものです。
シフトワーク
シフトワークとは、不特定のタイミングで深夜や早朝に働かなければならない仕事のこと。
体内時計のリズムが破壊され、ホルモンバランスの変化や睡眠の質の低下により、メンタルと身体に甚大な影響を及ぼします。

私の身内も夜勤がある仕事で、体調を崩して退職しました。
長時間通勤
毎日の長時間の通勤はストレスの原因になります。
私は地方在住なので満員電車とは縁がありませんが、考えるだけでもつらい…。
通勤時間が短いほどストレスが減らせる、かつ時間を有効に使えます。
長時間労働
働きすぎが心身に悪いのは常識ですね。
長時間労働のストレスは、確実に心身に悪影響を及ぼします。
厚生労働省は月80時間を超える時間外労働を過労死ラインとしていますが、週の労働時間が55時間超えると心身の崩壊に向かい出すそうです。
ワークライフバランスの崩壊
時間の乱れの中で、最も悪いのがワークライフバランスの崩壊です。
プライベートと仕事を切り分けずに働き続けることにより、うつ病の発症や不安障害のリスクが高まります。
さらに、プライベートの時間に仕事のことを考えるだけでも幸福度は激減してしまう。
- 休日に上司が連絡してくる
- 休暇中の仕事が当たり前の文化
このようなところは、要注意ですね。

私は休日でも結構仕事のことを考えてしまうタイプでした…。性格も大きく影響しますね。
職務の乱れ
職務の乱れとは、職務内容や環境の乱れ・欠陥により悪影響を及ぼすものです。
雇用が不安定
- 急に解雇される
- 安定(継続)して仕事がない
など、安定感のない働き方はストレスを感じます。
市場価値の高いプロフェッショナルは別にして、フリーランスのようなギグワーカーは、不安定な賃金や仕事がない不安などに向き合っていかなければなりません。
ソーシャルサポートがない
Google社の社内調査において、生産性の高いチームに必要なのは「心理的安全性であること」と判明しました。
心理的安全性とは、失敗やミスをしてもバカにされないし、助けてくれるだろうという組織に対する信頼感です。
ソーシャルサポートが大事なのは、人間が群れで生活していた動物であることに由来する脳のつくりが影響しています。
周囲に仲間がいないと、本能的に危機感を感じてしまうんですね。
仕事選びでは、以下のような視点が参考になります。
- 出世競争が激しすぎないか
- 社員が困ったときにサポートする体制や制度(福利厚生)があるか
- 交流イベントがあるか
仕事のコントロール権がない
コントロール権の有無については、幸福度を高める指標の「自由」で取り上げた内容です。
前述のとおり、自由があるほど幸福を感じる。
逆に、自分でコントロールできる自由度がないほど、不幸につながります。
組織内に不公平が多い
組織内の不公平は、幸福度を高める指標の「明確」で取り上げた内容です。
いくら頑張っても評価されない、
逆に頑張ってない人が評価される。
組織の不公平や理不尽が不幸につながります。
まとめ:幸せに働くためには、「なんとなく」ではなく「科学的な視点」で選ぼう
本記事の内容を要約します。
仕事選びや職場環境に対する不満や迷いは、多くの人が抱える悩みです。
しかし、「自分にとっての幸せな働き方」は、思いつきやイメージだけで判断すべきではありません。
この記事で紹介したように、幸福度を高める7つの要素、不幸につながる要因を知ることで、今の職場を客観的に見直したり、これからの仕事選びに必要な視点が身につきます。
これから転職を考えている方も、今の職場でモヤモヤを感じている方も、まずは「正しい知識」と「科学的な判断基準」を持つことが大切です。
もっと詳しく知りたい方は、今回の参考書籍である
『科学的な適職』(著:鈴木祐) をぜひ読んでいただきたいです。
まだまだ紹介したい内容が盛りだくさんです。
あなたのこれからの働き方を考えるヒントが、たくさん見つかります。
最後までお読みいただきありがとうございました。