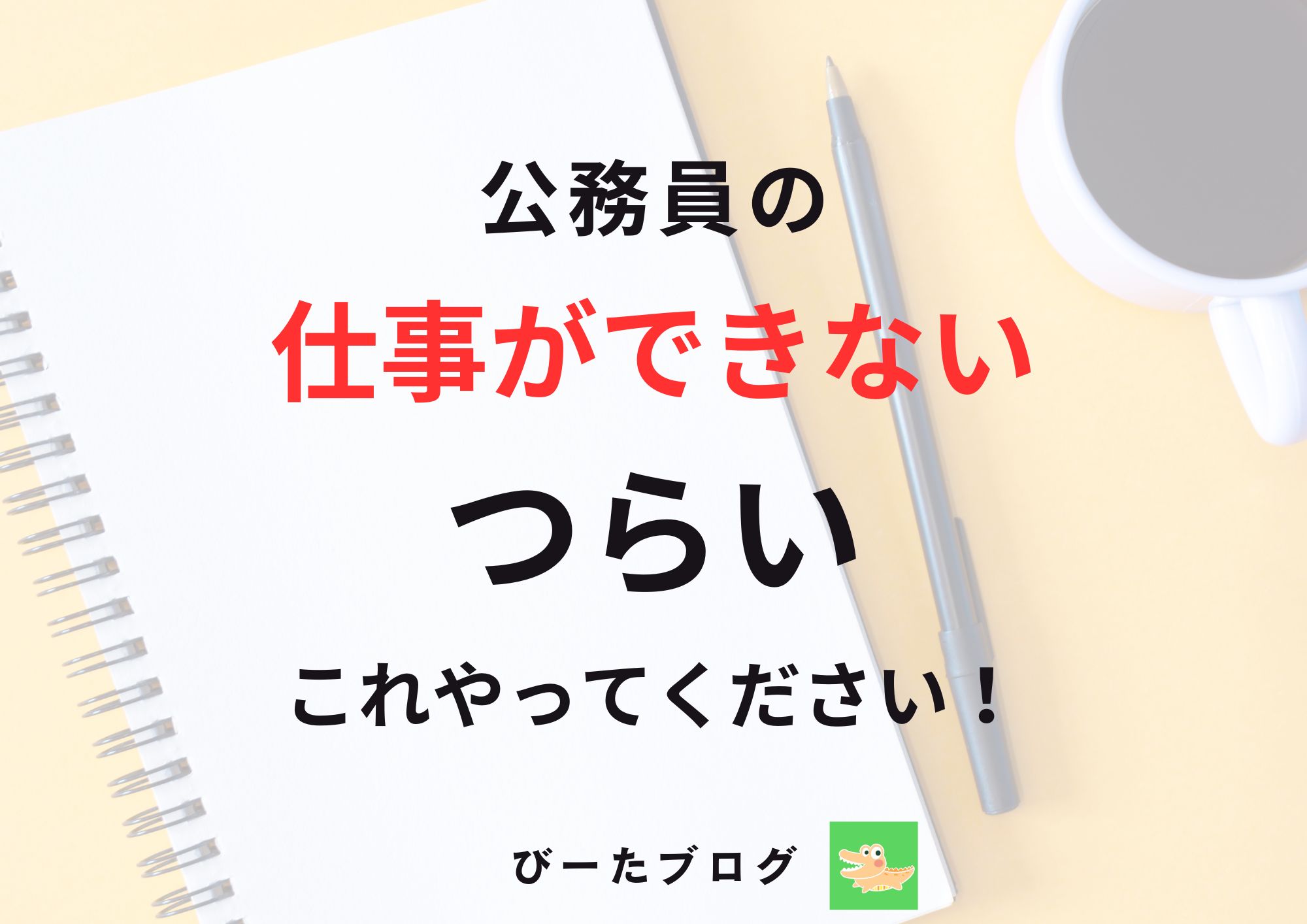公務員だけど、自分だけ仕事ができない…。
周りについていけない。
どうすれば仕事ができるようになるの?
こんな気持ちの方に記事を書きました。
公務員の仕事は定型的な業務でラク。
世間では、こんなイメージがあるかもしれませんが、公務員として働くとまったくそんなことはないですよね。
専門知識、調整力、資料作成など求められるレベルは高く、「仕事ができなくてつらい」と悩んで当然です。
私自身も仕事ができないと落ち込むことが何度もありました。
しかし、そこで終わるのではなく、対処法を先輩に聞いたり、本で調べたり試行錯誤することで、結果的に主要部署で仕事をこなすことができました。
この記事では、公務員の仕事が難しくてできないと悩んでいる方に向けて、仕事ができるようになる対処法をお伝えします。
県庁で14年働く中で、「この人仕事ができるなあ」と感じる人はたくさんいました。対処法では、その人たちが共通して実践していることがあります。
ぜひ参考にしてください。
公務員の仕事ができない、つらいと感じる状況

「仕事ができない…」と落ち込んでしまうタイミングはどんなときでしょうか。
いくつかありますが、大きく分けると以下5つになると思います。
- 知識・情報が足りない
- スキルが足りない
- 同じミスを繰り返す
- 段取りが悪い
- 時間がかかりすぎる
それぞれ解説します。
知識・情報が足りない
1つ目は知識不足だったり、情報が理解できてない場合です。
知識や情報が頭に入っていないと、自信を持って発言や説明ができないからですね。
- 説明を求められても答えられない
- 会議で発言できない
- 資料に必要な情報が抜けてしまう
自分が主担当として、最低限理解しておかなければいけないことがあります。
そこが理解できていないと、自分の意見も持てませんし、相手からの信頼も得られません。

自分の業務について、上司と先輩が話している内容が、全然理解できずポカーンとしてるときがありました。
スキルが足りない
2つ目はスキルが足りない場合です。
スキル(能力)の有無は、仕事のスピードや完成度に直結するからですね。
一言でスキルと言ってもたくさんありますが、特に公務員に必須なのが、以下3つです。
- 論理的思考力
- 文章・資料を作成する力
- コミュニケーション力
これらがすべて欠けているということはないですが、人それぞれ長短はありますよね。
日々の業務で必須のものになりますので、欠けているとつらく感じます。
同じミスを繰り返す
3つ目は、同じミスを繰り返す場合です。
公務員の仕事は、基本的にミス(失敗)は許されない環境なので、厳しく指摘されるからですね。
人間なのでミスをするのは仕方ないことです。
しかし、1回目のミスは多めに見られても、2回目のミスは上司も厳しく指導するでしょう。
「ミスしないように」と注意していても、ミスしてしまう。
こんなときは、かなり落ち込みますよね。

私も連絡事項を修正していなかったために、大多数の関係者に迷惑をかけた事件がありました…。
段取りが悪い
4つ目は、段取りが悪い場合です。
仕事によっては、関係部署を巻き込んで作業を分担して進めますし、個人でやるときも順番やタイミングが重要になるからですね。
段取りが悪いと、以下のような影響が生じます。
- 漏れの発生
- 二度手間
- 無駄に相手の時間を奪う
関係者に怒られたり、締め切りが過ぎてしまうこともあります。

県庁の仕事は、関係部署や市町村への依頼やとりまとめ業務が多く、段取りはかなり大事でした。
時間がかかりすぎる
5つ目は、業務に時間がかかりすぎる場合です。
どんな仕事にも締め切りがありますし、多数の業務をさばいていくためにはスピードがとても大事だからですね。
人手不足の影響などにより、公務員の業務量はどんどん増えています。
時間をかけないで、早く終わらせたいのに作業がなかなか進まない。
でも次の業務は、降ってくる。
仕事ができなくて、どんどんつらくなります。
公務員の仕事ができない、つらいときの対処法9選

仕事ができない状況は、日々の業務に一生懸命取り組んでいれば、改善していくこともあるでしょう。
が、もっと早く効率よく仕事ができるようになるには、考え方や行動を変えることが大事です。
仕事ができる人たちが実践している具体的な対処法は以下のとおり。
- 対処法1:考え方を考える
- 対処法2:報告・相談する
- 対処法3:スケジュール・タスクを見える化する
- 対処法4:早く取り掛かる
- 対処法5:質問を恐れない
- 対処法6:メモする、記録に残す
- 対処法7:自分でチェックする
- 対処法8:仕事ができる人をまねる
- 対処法9:スキルアップの努力をする
最初から全部やるのは難しいと思います。
できるところから、取り組んでいきましょう。
対処法1:考え方を考える
1つ目は、考え方を考えることです。
いきなり作業に入るのではなく、このステップを踏むことで、効率よく業務が進められるからですね。
仕事のゴールから逆算して以下を考えます。
- 業務の全体像を把握
- 業務のかたまりを細分化
- 必要になる情報や関係者を把握
- 段取りを組む
初めに考え方を固めておけば、あとは作業に落とし込めるので、スムーズに進めることができます。
難解で複雑に見える仕事でも、細かく分解すれば、小さく簡単な作業になりますよ。
対処法2:報告・相談する
2つ目は、上司や先輩に報告・相談することです。
知識や経験のある上司にアドバイスをもらえるし、業務の進捗を共有できるからですね。
対処法1で考えた「考え方」が正しければそのまま安心して業務を進められますし、間違っていれば修正ができます。
この早い段階で修正できれば、作業を進めた後のやり直しや追加作業など、何倍もの手間を省くことができますね。

仕事で一番効率が悪いことって、やり直しが発生することです。
どうしようもないときもありますが、無い方がいいですね。
対処法3:スケジュール・タスクを見える化する
3つ目は、スケジュールとタスクを見える化することです。
見える状態にしておくことで、作業の漏れを防いだり、次のタスクが明確になるからですね。
見える化する媒体は、使いやすく自分に合うものを選びましょう。
- スケジュール帳
- ノート
- ふせん
- エクセル
- アウトルック
デジタルか手書きかは、好みによりますね。
対処法4:早く取り掛かる
4つ目は、早くとりかかることです。(対処法1の「考え方を考える」を含む)
後回しにするほど、以下のような悪影響が生じるからですね。
- 仕事の見積もり時間がズレたときに対応できない
- 後からは、さらに忙しくなっている
- やらないといけない(けどやってない)ストレスが常にかかる
そして最悪の場合、締め切りを守れない。
正直なところ、私の経験上では仕事ができるなと感じた人で、取り掛かりの遅い人はいませんでした。
こちらから依頼したときの、質問やレスポンスもめちゃくちゃ早いです。

「締め切りが近くなって追い込まれないとやる気がでない」とか言ってる人は、ほぼ締め切りを守りません!
対処法5:質問を恐れない
5つ目は、質問することを恐れないことです。
わからないことは全く恥ずかしいことではないですし、わからないままにして進める方が悪だからですね。
「そんなこともわからないのか」と言われるのが怖くて、質問に躊躇してしまう人もいるでしょう。
でも、そのわかってない状況で進めてミスや二度手間が生じるよりは100倍マシです。
質問するだけで、仕事に責任を持って向き合っていることになります。
何度も同じ質問をするのはよくないですが、曖昧なままにするのはやめましょう。
対処法6:メモする、記録に残す
6つ目は、メモしたり、記録に残すことです。
人間の脳はすぐ忘れるようにできているので、記憶力は全く信頼できないからですね。
人に質問したり、会議がある場合は、必ずメモを取りながらのぞみましょう。
メモ内容は、対処法3のスケジュールやタスクに落とし込んで活用します。
また、自分の考えを整理するためにメモを活用するのも有効です。
箇条書きで羅列してみたり、オリジナルの図を書いてみたりすると思考がクリアになりますよ。

メモをとる姿勢があれば、本気度が示せますので教えてくれる人も丁寧に対応してくれます。
対処法7:自分でチェックする
7つ目は、作成したものを自分でシングルチェックをすることです。
資料を作成している段階で、必ず小さなミスは発生するからですね。
自分でシングルチェックすることで、誤字脱字、文章の誤り、計算ミス、ズレなど必ず修正点が見つかるはずです。
決裁を回す前や上司に見せる前に、自分でミスを修正する癖をつけましょう。

私自身、資料作成後は人に見せる前に必ずシングルチェックをしていました。
対処法8:仕事ができる人をまねる
8つ目は、仕事ができる人のまねをすることです。
まねをすることが、自分が成長するための一番の近道だからですね。
仕事ができる人には、それだけの理由があります。
100%生まれ持った才能だけで、完璧に仕事ができる人はいません。
意識の有無にかかわらず、結果を生み出すために何かしらの行動をしているのです。
「その人の行動の中で、まねできるところがないか」という意識で、観察してみましょう。
対処法9:スキルアップの努力をする
9つ目は、スキルアップの努力をすることです。
業務だけをしていても、身につけられない知識や能力がたくさんあるからですね。
自分を成長させたい人は、日頃からスキルアップのために自己投資しています。
投資方法は、読書、資格取得、自主勉強など様々です。
人にはなかなか見せない部分ですが、やる人はしっかりやっていますよ。
私の同僚は、業務で使用する法令の参考書を自費で買って勉強してました。

私も大量のデータを扱う部署に異動になったときは、エクセルの数式をかなり勉強しました。
それでもつらいときの対処法
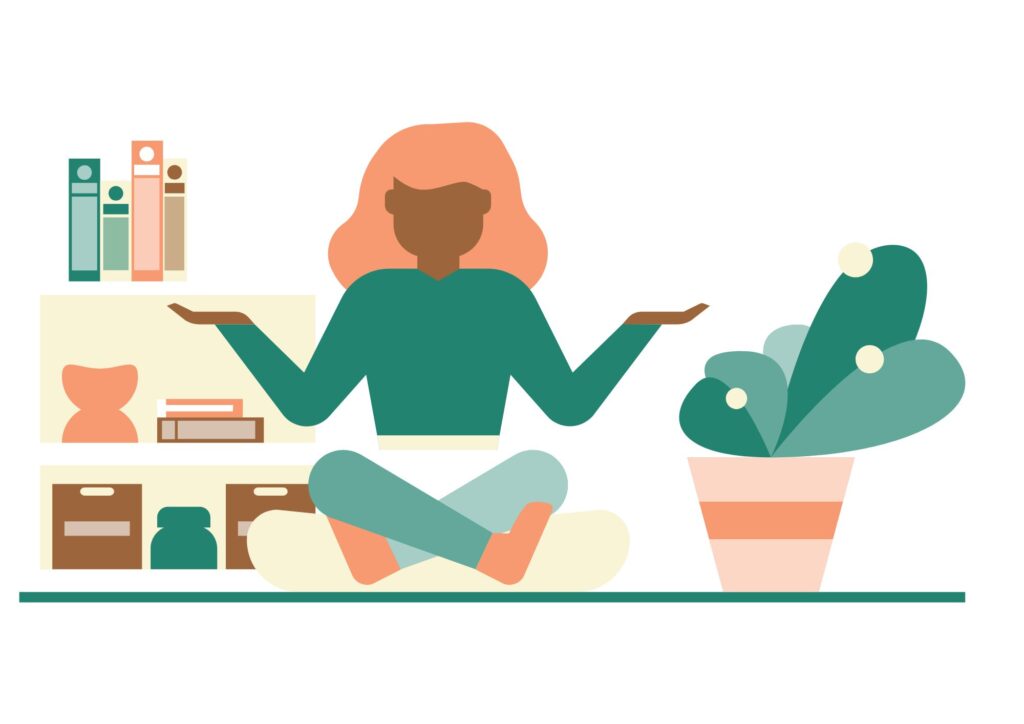
仕事ができなくてつらいときに実践できる対処法を見てきました。
しかし、個性や適性は人それぞれ。
どうしても、今の職場はつらくて限界という人もいるでしょう。
そんなときは、自分の心身を守ることやキャリアの方向性を変える方向に解決方法をシフトしてください。
具体的には以下の3つ。
- 休職する
- 異動希望を出す
- 転職を検討する
それぞれ見ていきましょう。
休職する
体と心の不調を感じたら、心身を休めることが重要です。
メンタルダウンは、あなた自身や家族、職場など誰にとってもマイナスでしかありません。
公務員の仕事は組織で回っているので、1人休んでも全然なんとかなります。
「仕事でメンタルこわすのは、バカらしいくらい」の心持ちでいきましょう。
異動希望を出す
異動希望を出すことも有効です。
現在の業務の特殊性や人間関係が根本的な原因で、つらいという場合もあります。
異動できる可能性を少しでも上げる努力はするべきです。
ただし、人事異動は個人の希望より組織の都合が優先されるため、簡単に希望は通りません。
上司に相談したり、異動希望調書の書き方を工夫するなど対策しましょう。
こちらも参考にしてみてください。
-
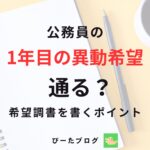
-
公務員の配属1年目の異動希望は通る?元公務員が解説します
2025/7/28
こんな疑問をお持ちの方に記事を書きました。 この記事の内容 ・配属1年目の異動が難しい理由・配属1年 ...
転職を検討する
公務員の仕事がどうしても合わない場合は、転職という手段もあります。
公務員は膨大にある仕事の中のひとつでしかありませんし、根本的な向き不向きがあるからですね。
これから経験年数が上がるにつれて、任せられる業務の難易度は上がります。
また、定期的な異動により、積み上げた知識は何度もリセットされます。
今後の人生を長期的に考えたときに、転職した方がメリットが大きいと判断できれば、転職活動を始めるのも選択肢のひとつです。
まとめ
本記事の内容を要約します。
仕事ができなくてつらいと感じるのは、誰もが経験することです。
つらいと感じているということは、成長の機会を与えられていると前向きに考えることもできます。
身の回りの先輩や上司も、同じようなつらさを経験しつつ、対処するために行動することで仕事ができるようになっているはず。
仕事が少しずつできるようになると、見る視点が変わったり、さらにやる気が出るなど、前向きな変化も起こります。
無理しない範囲で、できる対処法をやりながら成長していきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。