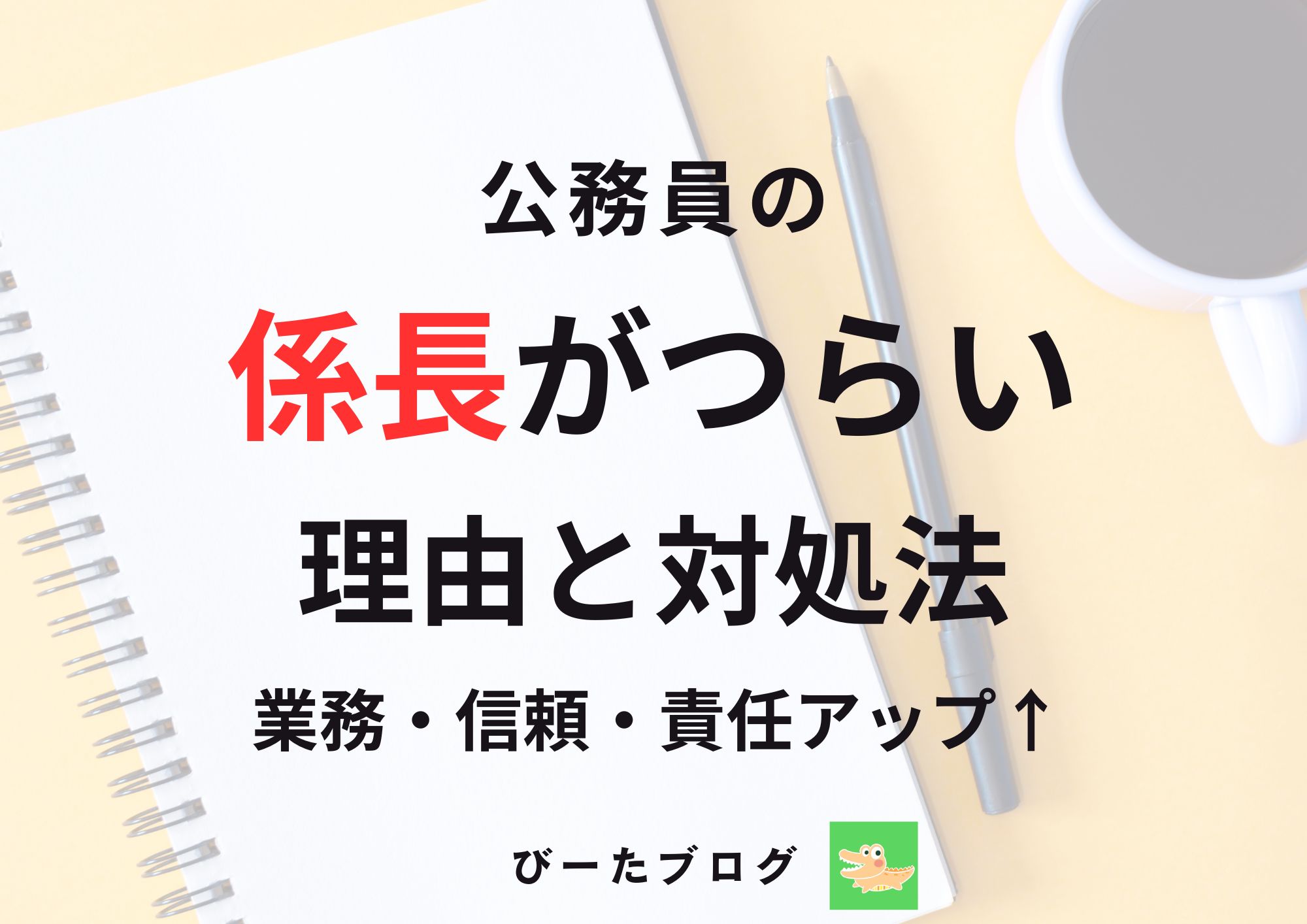公務員の係長に昇進したけど、毎日がつらい…。
どう乗り越えていけばいいの?
こんな気持ちの方に記事を書きました。
県庁の仕事は係長で回っている。
昔の上司から聞いた言葉がずっと印象に残っていますし、個人的にもそのとおりだと思っています。
担当の職員をマネジメントしつつ、現場の業務を管理・推進する要(かなめ)の役割。
だからこそ、やりがいと同時に大変なことも爆増します。
私も同僚とよく「係長は大変だよね」という話をしていました。
この記事では、県庁で勤務した経験を踏まえて、公務員の係長がつらいと感じる理由と対処法をお伝えします。
ぜひ参考にしてください。さっそく見ていきましょう。
\毎日の積み重ねで実力アップ/
スキマ時間にスマホで、グロ放題。GLOBIS 学び放題公務員の係長がつらい理由
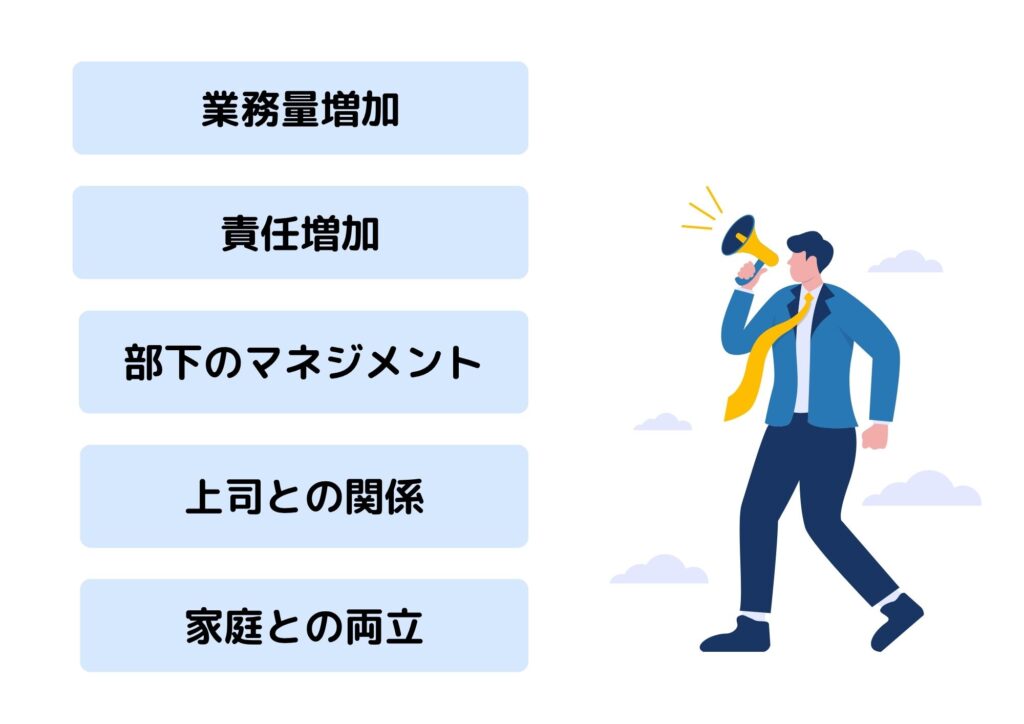
係長がつらいと感じる理由を4つ挙げます。
- 業務量が増加する(プレイングマネージャー)
- 責任がのしかかる
- 上司と部下に挟まれる
- 家庭やプライベートと両立できない
それぞれ解説します。
業務量が増加する(プレイングマネージャー)
1つ目は業務量が増加することです。
部下全員の業務マネジメントをしないといけないですし、部署によっては自分の担当業務を持っているからですね。
- 大量の決裁文書のチェック
- 部下の相談対応
- 担当全体の進捗管理
- 上司への報・連・相
- 加えて、自分の所管業務
担当のときは自分の業務内容を把握できていれば何とかなりますが、係長になると全体の業務内容を把握する必要があります。
課長や部長は、係長に質問してきますからね。
大量のタスクをこなしつつ、勉強していかなければなりません。

初めての業務分野で係長になると、内容がよくわからないけどマネジメントするという超絶ハードモードな状態になります。
責任がのしかかる
2つ目は責任が一気に増すことです。
問題が起きたとき、建前では部長や課長が責任を問われます。
が、実態としては係長が責任を感じることになります。
理由としては、以下のような感じです。
- 課長は係長のことを信頼して詳細は確認しない
- 係長が一番現場に近いところでマネジメントしている立場
- 係長が担当職員のせいにするべきではない
判断の正当性や決裁の正確性は、係長を出たところで9割決まっていると言っても過言ではないと思います。
それくらいの質が求められるからこそ、責任は重大です。

担当のときは「係長がチェックするからいいか」という甘えがあるかもしれませんが、係長はそれができないですね。
上司と部下に挟まれる
3つ目は、中間管理職ならではの上司と部下との関係です。
上司も部下も自分で選ぶことはできませんが、上手に付き合っていく必要があります。
部下との関係
優秀で仕事ができて、自分の指示を素直に聞いてくれる。
こんな部下が理想ですが、そう甘くはありません。
- 仕事をしない
- 指示しないと動かない
- トラブルばかり起こす
- 指示に反発する
- 知識でマウントをとってくる
- メンタル不調気味
こういう部下に当たると、マネジメントに手を焼きますね。

ガチャ要素がありますが、こういうちょっとクセのある職員が少ないのが、激務の職場だったりするという皮肉…。
上司との関係
上司にも多様なパターンがあります。
- 高圧的な態度
- 指示があいまい
- 重要性が低いところで細かすぎる
- 係長に丸投げ
どれが当たっても、精神的にきついです。
公務員の世界は年功序列なので、優秀だから課長というわけではありません。
年功序列制度の良くない部分ですね。
家庭やプライベートと両立できない
4つ目は、仕事と家庭の両立ができないことです。
係長くらいの年齢になると、結婚したり、小さなお子さんを育てるタイミングと重なる傾向があります。
仕事だけに専念できた時とステージが変わる感じですね。
- 業務が多くて帰れない
- 家庭のことに時間がとれない
- パートナーが大変そう
- パートナーから愚痴を言われる
ただでさえ職場が大変な状況なのに、家庭環境も安定しないと精神的にかなり追い込まれます。
自分もパートナーも追い詰められて、ぶつかってしまうこともあります。

私は激務の職場が続いたので、家庭との両立はムリゲーでした。
退職を考えた要因のひとつですね。
公務員の係長がつらいときの対処法

係長がつらいと言っても、やらなければいけないのが組織のルール。
勤務年数を重ねれば、エスカレーターで係長になりますので、しっかりと向き合って対処する必要があります。
紹介したい対処法は以下の6つです。
- 対処法1:マネジメントを勉強する
- 対処法2:選択と集中を行う
- 対処法3:上司・部下と向き合う
- 対処法4:割り切る
- 対処法5:しっかり休む
- 対処法6:キャリアを見直す
それぞれ見ていきましょう。
対処法1:マネジメントを勉強する
マネジメントの勉強をすることは有効です。
マネジメントスキルの知識がないまま、思いつきや感覚でやってもうまくいく確率が低いからですね。
担当職員と係長ではステージが違うので、求められるスキルが異なります。
係長に昇進して職場で1~2日受ける研修だけで、十分な知識が身に付くでしょうか。
組織で働く上では、公務員も企業も同様のスキルが必要になってくるため、体系的にまとめられた情報はたくさんありますよ。
- 本を読む
- ネット記事を調べる
- 動画で学ぶ
- オンライン講座を受ける
知識を集めて(インプット)、職場で実践する(アウトプット)という繰り返しによるスキルアップが必要です。
スキマ時間にスマホで、グロ放題。GLOBIS 学び放題
マネジメントがうまい上司のもとで働く方が、部下は絶対幸せですよ。
対処法2:選択と集中を行う
タスクの選択と集中を行い、時間を有効に使う必要があります。
膨大なタスクがある中で、すべてを完璧にこなすのは無理だからですね。
- 無駄な業務を減らす(やめる)
- 効率が悪いことはやり方を変える
- 部下ができるものはまかせる
日々、このような意識を持って取り組むことが大切です。
とはいえ、独りよがりですべてを決めてしまってはトラブルのもと。
自分が無駄・効率が悪いと思っている感覚と、部下や上司の感覚は違うかもしれないです。
コミュニケーションをとりながら、対応していく必要があります。
対処法3:上司・部下と向き合う
上司・部下との良好な関係性の構築は、避けずに向き合うべきです。
避けていても、結局仕事がうまく進まないからですね。トラブルの発生など、余計な仕事が増えることもあります。
重要なのは、個性の把握とコミュニケーションです。
個性の把握
人間は価値観や考え方、好き・嫌い、得意・不得意はそれぞれ異なるものです。
仕事にしても、以下の例のような違いがあります。
| 自分にまかせてほしいタイプ | 確認しながらチームで進めたいタイプ |
| 感覚で決めるタイプ | 論理的に考えるタイプ |
| チャレンジ派 | 慎重派 |
| 理想主義 | 現実主義(リアリスト) |
| モチベーション高い | モチベーション低い |
| 能力高い | 能力低い |
| 仕事重視 | プライベート重視 |
個性にグラデーションはあるので、完全に型にはめる必要はありませんが、上司や部下のおおよそのタイプは把握できるはず。
その人に適合した方法で、マネジメントしないと相手にストレスがかかり、スムーズに進まないことになります。
よく観察して、その人なりのおおまかなタイプを把握しましょう。

Disc診断や類人猿診断などいろいろな分け方がありますね。
自分もどれに当たるか見てみるとおもしろいですよ。
コミュニケーション
上司や部下とのコミュニケーションは、とりすぎるくらいとった方がいいです。
相手の考えや悩みは、想像していてもわからないからですね。
- 定期的な1on1ミーティング
- 飲み会やランチでの会話
- 日常の会話
機会はつくれますし、既存の機会を活用することもできます。
コミュニケーションを重ねることで、信頼性が増せばさらに相手が考えや悩みを開示してくれる。
信頼関係があれば、こちらの意見にも耳を傾けてくれますし、同じ方向性を向くことで仕事がしやすくなりますよ。

会話では、最初から否定したり決めつけたりせず、話を聞くことが大事ですね。
コミュニケーション術もいろいろ勉強できます。
対処法4:割り切る
できないことは割り切る気持ちも大事です。
全てを完璧にすることなんてできないですからね。
最初からすべてを放棄するのではなく、いろいろと試行錯誤した上で割り切る感じです。
コントロールして変えられるものと変えられないもの
この視点で、物事を考えることも有効です。
対処法5:しっかり休む
自己管理のためにしっかり休むことも重要です。
マルチタスクやストレスにより、体力面・精神面で大きな負荷がかかっているからですね。
- 睡眠時間をしっかり確保する
- リフレッシュ時間を組み込む
- 家庭・プライベート時間を確保する
しっかり休む時間を作るために、仕事をどうマネジメントしていくかを考えていくことになります。
また、どうしてもメンタル的にきついときは、躊躇せずに対応してください。
メンタルダウンしてしまっては、自分、家族、職場、誰にとってもいいことはありません。
「代わりはいくらでもいる、結局どうにかなる」のが組織の強みです。
躊躇する必要はありません。
対処法6:キャリアを見直す
本当に自分に合わないと感じたらキャリアを見直すことも選択肢のひとつです。
公務員の仕事は、決して楽な仕事じゃありませんからね。
向き・不向きの適性だったり、ストレス耐性の限界は考えるべきです。
仕事は人生を幸せにするための手段であって、目的ではありません。
- 転職活動をする
- キャリアコーチングを受けてみる
- 自己分析で自分を見直す
- 将来の独立のためにスキルを身につける
始められることはたくさんあります。

公務員の仕事以外にも、活躍できる場はいくらでもありますよ。
つらい係長経験を経て手に入れられるもの

係長の立場がつらいと感じる一方で、経験を通して手に入れられるものもあります。
具体的には以下の3つ。
- マネジメントスキルの獲得
- 裁量権の拡大
- 自分と部下の成長
それぞれ見ていきましょう。
マネジメントスキルの獲得
マネジメントスキルは、今後の仕事をしていく上で最強レベルの武器になります。
複数の人が集まって仕事をする以上、マネジメントできる人材が必須だからですね。
- 出世しても活かせる
- 転職市場でも武器になる
- 独立しても使える
最強のポータブルスキルです。

転職サイト・エージェントの登録でも、マネジメント経験の有無は必ず聞かれますよ。
裁量権の拡大
係長になると、業務判断の自由度が上がります。
現場に近いところでマネジメントしている分、専門知識も蓄積されるからですね。
対外的な説得力も増しますし、課長や部長も尊重してくれる傾向があります。
自分の判断で行政が動かせる感覚は、やりがいも上がるものです。
自分と部下の成長
つらいと感じる環境は、自分の成長につながります。
ストレスがかからないと成長することはできないからですね。
また、自分のマネジメントで部下を成長させられることも大きなやりがいです。
自分が部下を選べないように、部下も上司を選べません。
自分の適切なマネジメントによって、部下の成長に貢献できることは係長ならではの幸せです。

その部下が係長になったときに、理想像にしてもらえる存在になれるとうれしいですね。
まとめ
本記事の内容を要約します。
公務員の係長は、まさに組織の“要(かなめ)”です。
現場を回し、部下を支え、上司に説明し、そして自分の仕事もしっかりこなす。
やりがいもありますが、それ以上にプレッシャーや負荷も大きく、心身ともに追い詰められやすいポジションです。
しかし、だからこそ得られるものも確かにあります。
マネジメント力、判断力、部下とともに成長する喜び――。
これらは、今後のキャリアにおいて大きな財産になるはずです。
つらいときは我慢だけで乗り越えようとせず、適切な対処法を取り入れたり、キャリア全体を見直したりすることも大切です。
自分を守れるのは自分しかいません。
「実力をつける」「割り切る」「休む」のバランスで乗り越えていきましょう。
この記事が、がんばる係長のみなさんの一助になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
\実力アップは、自分とチームの幸せにつながる/