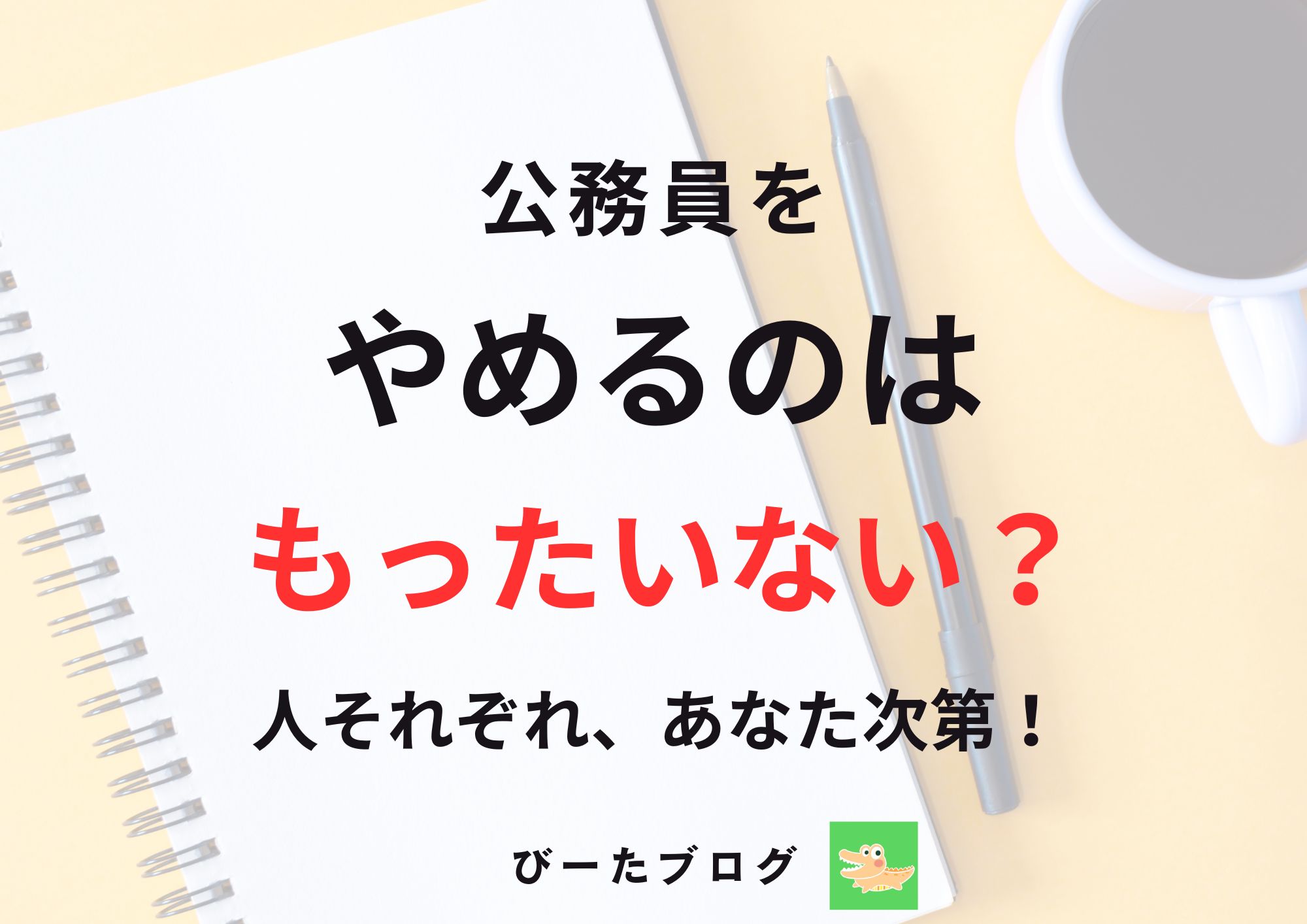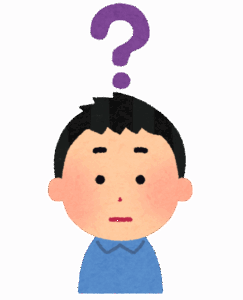
公務員を辞めるのは、もったいないと言われる…。
本当にもったいない?ほかの考え方もあるのでは?
こんな気持ちの方に記事を書きました。
公務員を辞めようか悩んでいると相談したら、もったいないと反対される。
私もやめる前、辞めた後に多くの人に「もったいない」と言われました。
10年前ならば、私自身も同じように「もったいない」と反対していたと思います。
結論としては、もったいないかどうかはその人次第です。
改めて認識しておいてほしいことは、もったいないと言ってくる人とは、
- 公務員の仕事に対する情報量が違う
- 価値観が違う
- 自分ごとではない
という前提があります。
なので、他人の意見ではなく、自分で決めるしかありません。
とはいえ、自分で決めることがいかに難しいかは、私も5年以上決断できなかったので痛いほどわかります。
この記事を読んで、公務員をやめるか悩んでいる方が、これからのことを判断するヒントにしていただけるとうれしいです。
さっそく見ていきましょう。
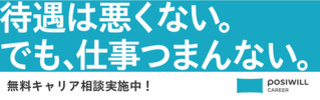
公務員を辞めるのがもったいないと思うのは当然のこと
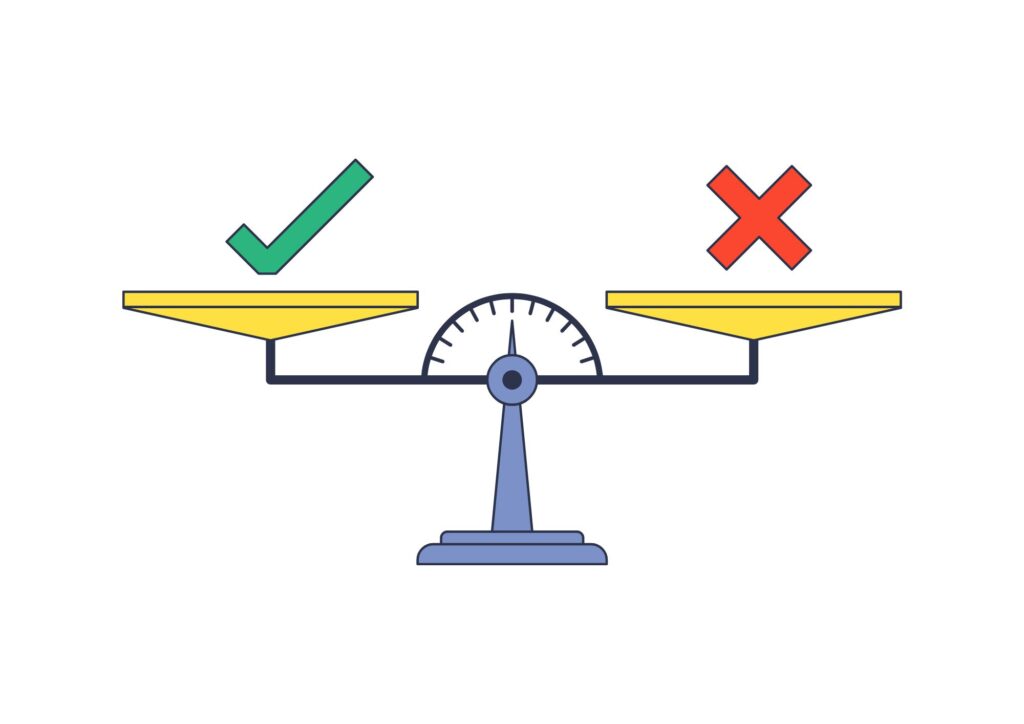
公務員を辞めること自体を、もったいないと思うのは当然のことです。
苦労した就職した経験や費やした時間など、積み上げたものを手放すことになるからですね。
合理的な判断のじゃまをする認知バイアス(考え方の偏り)にサンクコスト効果というものがあります。
サンクコスト効果とは、今までたくさんの時間やお金を使ってきたことを理由に、メリットがない選択肢にこだわり続けてしまうこと。
公務員を続けることが、デメリットになるかどうかは人それぞれです。
が、明らかにデメリットである人にとっても、経験年数が長くなるほど、サンクコスト効果の影響は大きくなることは理解しておくといいと思います。

「せっかく~したから、(合理的に考えて間違っているのに)辞められない」という状況ですね。
公務員を「辞めるのがもったいない」と言われる理由

一般的に公務員を辞めるのがもったいないと言われる理由を挙げます。
- 収入・身分の安定
- 社会的信用の高さ
- 誰でもなれない貴重性
- 辞めた後にうまくいくとは限らない不確実性
それぞれ見ていきましょう。
収入・身分の安定
公務員は、収入面や身分保障の安定性が高いです。
法令により給与は定まっていますし、懲戒免職などを例外として、解雇されることはないからですね。
- 毎年の昇給
- 年功序列による昇進
- ボーナス約4か月分の支給
- 充実した福利厚生
これらが確約されているというのはやはり強いです。
この待遇を捨てるのはもったいないという意見が出るのは当然でしょう。
社会的信用の高さ
給与や身分の安定に付随して、社会的信用も高いです。
難しい試験を突破しているため、頭がいいというイメージがありますし、身分も保証されているからですね。
- 親戚からの評判
- 結婚相手としての評価
- 知り合いからの信頼度
- ローン審査などの評価
いずれも想像以上に高い評価を受けることができます。
誰でもなれない貴重性
誰でもなれるわけではないという貴重性から、もったいないという意見も出ます。
難関の公務員試験を突破するのは、簡単ではないからですね。
- 教養・専門試験の膨大な試験対策を行う
- モチベーションを維持して勉強する
- 論文試験、面接をクリアする
ある程度の基礎学力や継続する努力が必要です。
現在は受験者数の減少により、受験しやすいように難易度が下がってきています。
が、一定の人気があることは変わらず、誰でも簡単になれるわけではありません。

公務員に採用されたときは、めちゃくちゃうれしかったのを覚えています。
14年後に自らやめるとは夢にも思いませんでした。
辞めた後にうまくいくとは限らない不確実性
辞めた後の転職や起業がうまくいくとは限らないことも、もったいないという意見を生み出します。
人間は、何かを得ることよりも失うことを重要視するからですね。
失うリスクを最小化する行動を選らぶ。
公務員という職業を選択した人は、安定・安心を重視する傾向があるので、この感情は一段と大きいかもしれません。
公務員を「辞めるのがもったいない」への反論
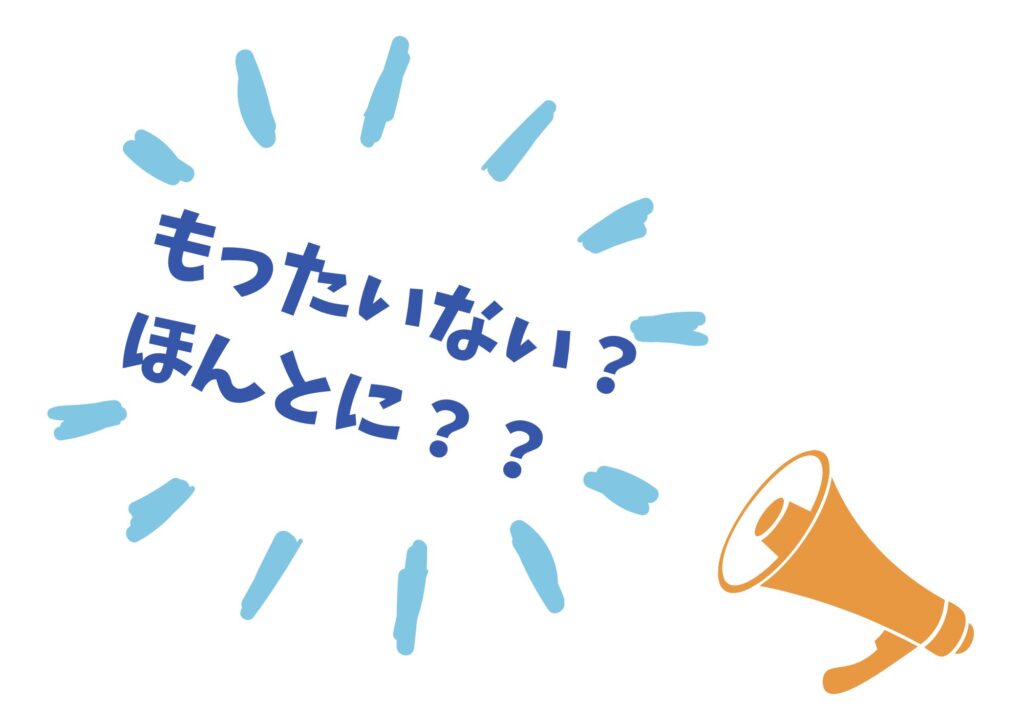
辞めるのがもったいないと言われることに対して、反論意見を挙げます。
反論意見は、公務員を実際に経験し、内側から見てみないとわからないことばかりです。
この記事を読んでいる公務員の方も共感する部分が多いはず。
具体的には以下の4つです。
- 本当の安定は手にしていない
- 厳しい勤務環境
- 自分のキャリアを選択しづらい
- 不安や苦労を乗り越えなければ手に入れられないものがある
それぞれ解説します。
本当の安定は手にしていない
公務員が安定していると言われることは前述したとおりです。
しかし、もう少し確度を上げて言うと、「公務員を絶対に辞めない限りにおいて安定」ということです。
「辞めなければいいじゃん」となりそうですが、そこが難しいポイントです。
なぜなら、自分の価値観や周りの状況は変わる可能性があるから。
どうしても転職したくなることもあれば、どうしても転職せざるを得ない状況になることはあり得ます。
- 自分の考え方の変化
- 家族の介護、子育てなど状況の変化
- メンタルや体調の変化
- 公務員制度の変化(長期的には不明)
本当の安定とは、組織に固執せず、自分でコントールできる柔軟な選択肢を持っていることだと思います。
選択肢が1つしかなければ、どうにかしてしがみつくか、しがみつけないときに苦労するしかありません。
安定の考え方は、人によって全く異なります。
公務員という箱の中にいることに固執している方が、不安定とも言えるのです。
厳しい勤務環境
公務員は労働量やストレスの面で、決してラクな仕事ではありません。
県庁で14年勤務した経験から自信を持って言えますし、今後はさらに厳しくなっていくと思います。
- 業務量を自分達でコントールできない構造
- 人口減少及び公務員の魅力低下による人手不足
- 人手不足に逆行する業務量増加
- 優秀な人が辞め、しがみつくものが残る構造
- 仕事ができる人に仕事が集まる傾向
- 強いストレスにさらされる環境
現役の公務員の方ならば、実感している方が多いと思います。
こちらの記事に、関連する内容をまとめました。
-
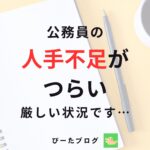
-
【公務員は人手不足です】現状と現場で起こることを元公務員が解説します
2025/7/28
こんな疑問をお持ちの方に記事を書きました。 この記事の内容 ・公務員の人手不足の現状・公務員の人手不 ...
自分のキャリアを選択しづらい
公務員は、キャリアをほとんど自分で選択できません。
特に行政職は、様々な業務や部署を経験させることで、ジェネラリストとして成長させる目的があります。
また、定期的な異動は、個人の希望より組織の都合が優先されます。
- まったく興味のない仕事
- やる意味を見出せない仕事
- イヤでたまらない仕事
- 自分の強みが活かせない仕事
これらに多大な時間をかけて取り組んでいくことが基本です。
「仕事とはそういうものだ」という考えもありますが、本当にそうでしょうか。
自分で選択できるということが、幸せにつながると思います。

異動先の業務がイヤで、ひたすら次の定期異動まで我慢して働くのが幸せとは思えないです。
不安や苦労を乗り越えなければ手に入れられないものがある
公務員の職から離れて、現状より良い状況になるかどうかはわかりません。
幸せになるかもしれないし、後悔するかもしれない。
しかし、環境が変われば、一時的に不安を感じたり、苦労するのはある意味当然です。
公務員なら定期異動の環境変化で、何度も経験しますよね。
転職や起業は、1回しかできないというルールはありません。
後悔したり不満を感じたら、さらに良い仕事(環境)を求めて動き続ければいいだけです。

公務員の転職に関しては、一度転職して民間経験を積めば、さらに転職のハードルが下がるメリットがあります。
解決策1:自分へ問いを立ててみる
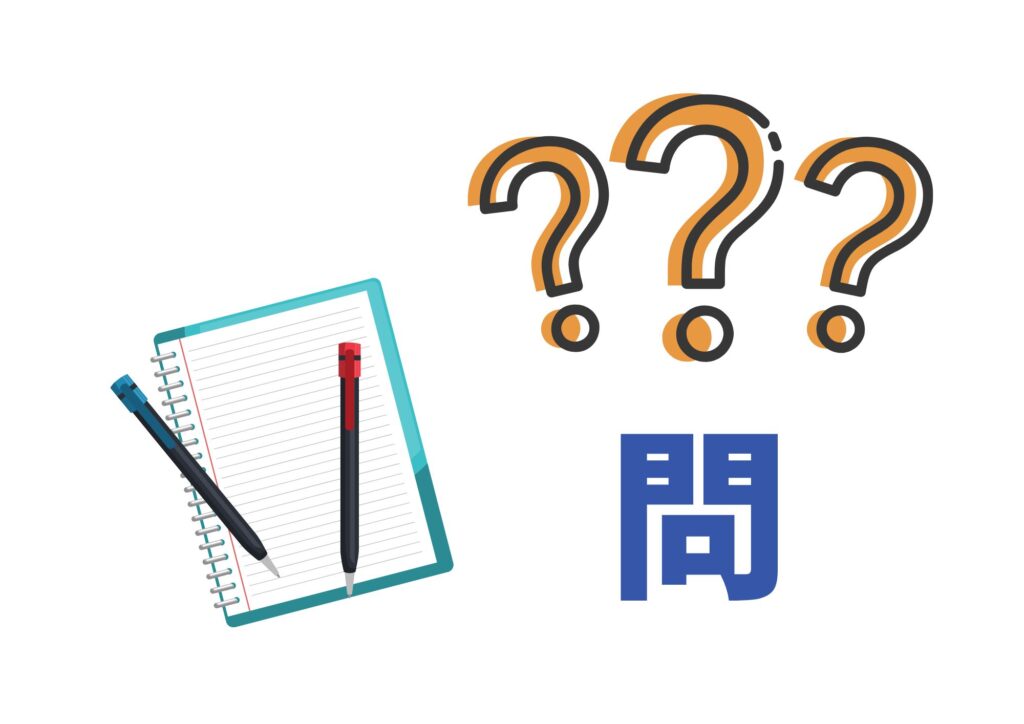
公務員を「辞めることがもったいない」という意見と反論を見てきました。
じゃあ結局どうすればいいのかと、さらに悩む方もいるかもしれません。
私が最初に実践してみたのは、自分に問いを立てて、じっくり考えてみることでした。
具体的には以下のとおり。
- 今の悩みは辞める(転職)以外で解決できないか
- 自分にとって仕事とは何か
- 今後の人生はどうありたいのか(どうなりたくないのか)
- 今の悩みを解消するために、具体的に何をすればいいか
今の悩みは辞める(転職)以外で解決できないか
公務員を辞めたい・転職したいと考える悩みの要因は、ほかの方法で解決できないのかを考えます。
辞めなくても解決できるならば、わざわざやめる必要はないですからね。
- 人間関係
- ハラスメント
- 業務内容
これらは、部署異動や休職でも解決できる可能性が高いです。
また、人間関係の悩みは転職したとしても、組織で働く限りどこでも起こりうるものです。
悩みの要因は、じっくり整理しましょう。
自分にとって仕事とは何か
仕事に対する価値観や考え方も人それぞれです。
- やりがいや幸せを感じたい
- 自己成長して貢献したい
- できるだけラクしたい
- 生活に困らないお金を稼げればよい
- たくさんのお金を稼ぎたい
公務員の仕事で、できるものとできないものがありますよね。
自分にとって、仕事に求めるものは何かを整理しましょう。

あと30年程度働く上で、この価値観と公務員の仕事にズレがあるとつらいですよね。
今後の人生はどうありたいのか(どうなりたくないのか)
若いときは、目の前の仕事をこなして、プライベートを楽しんで充実した時間が過ぎやすいです。
しかし、少し落ち着いてくると、ふと立ち止まることがあります。
これまで見えなかったものが見えてきたり、見る立場・視点が変わるからですね。
そんなとき、今後の人生はどうありたいのか、またはどうなりたくないのかを一度整理することが有効です。
もちろん、こうありたいと思っても不確定要素だらけで、未来のことはわかりません。
それでも、自分でコントロールできる方向性だけは、大事にした方がいいと思います。
今の悩みを解消するために、具体的に何をすればいいか
何か行動しない限り、悩みは解消することはありません。
めちゃくちゃ運が良くて、悩みがすっかり解消される出来事が起こることはほとんどないですよね。
おそらく、待っていても何も変わりません。
悩みを解消するために、
- 具体的に何をすればいいのか
- 今から始められることは何か
を考えてみましょう。
次の段落で、行動内容をいくつか紹介しているので参考にしてみてください。
解決策2:行動する
前述したとおり、何か行動しない限り、悩みが解消する可能性は低いです。
また、行動することで、さらに判断材料が集まるので、適切な判断につながりやすいメリットがあります。
公務員を辞めるのがもったいないのか悩んだときに、提案したい行動は以下の4つです。
- 転職活動をしてみる
- 信頼できる人またはプロに相談する
- 実際に辞めた人に話を聞いてみる
- パートナーに相談する
転職活動をしてみる
自分の価値観を確認できたら、転職活動をしてみることは有効な行動です。
転職活動を通して、自分自身と徹底的に向き合うことになりますし、応募することで具体的な結果が返ってくるからですね。
- 求人を探す
- エージェントのヒアリングを受ける
- 自己分析をする
- エントリーシートを書く
労力はかかりますが、その代わりに情報、気づき、経験など得られるものも膨大です。
転職活動を通して、やっぱり公務員が最適と判断できる可能性もあります。
信頼できる人またはプロに相談する
心から信頼できる人がいれば、相談してみるのもよいと思います。
一般論でなく、あなたの価値観や悩みの本質の部分からアドバイスをしてくれるかもしれません。
また、キャリアコーチなどプロに相談する選択肢もあります。
費用はかかりますが、人生のかかった決断になりますし、キャリアのプロは同じような悩みは何度も受けています。
客観的な視点やこれまでの相談経験を踏まえた視点で、解決策のヒントがもらえます。
(キャリアに特化したコーチング・サービス【POSIWILL CAREER(ポジウィルキャリア)】の無料キャリア相談への申込み)実際に辞めた人に話を聞いてみる
もし、知り合いで既に辞めた人がいるのなら、話を聞いてみるのも有効です。
実体験を通しての感想や注意点をを聞けるかもしれません。
人は同じ悩みや境遇の人に、やさしくしたり、手を貸したくなるものです。
親切に相談にのってくれる方が多いと思います。

私も、同じような悩みで相談を受けたら、全力で応援したいと思います!
パートナーに相談する
既に結婚したり、結婚予定がある方は話をしておくべきです。
パートナーにとってもかなり大事なことなので、相談していないことが揉める原因になるからですね。
相談のコツは、自分だけのメリットでなく、相手にとってもメリットがあるように相談すること。
- 今より家庭の時間が増やせる
- 収入が増える可能性がある
- 通勤や転勤の負担が減る
- メンタル崩壊の危険が少なくなる
相手が受け入れやすい話題にすると応援してくれる可能性が高まります。

うちは、私がかなり悩んでいたので、割とすんなりOKしてくれました…。
まとめ
本記事の内容を要約します。
公務員を辞めるのは「もったいない」と言われるのが当たり前です。
安定や信用、待遇の良さは確かに魅力ですが、それが本当に自分にとっての幸せや安定につながるかは人それぞれ。
他人の意見には、その人の価値観や情報量、立場が反映されています。
最終的な判断は、自分の価値観と人生の方向性に基づいて決めるしかありません。
そのためには、現状の悩みや将来のビジョンを整理し、解決策や行動プランを具体的に描くことが重要です。
転職活動や信頼できる人、プロへの相談など、行動を通じて判断材料を集めれば、後悔しない選択につながります。
「もったいない」に縛られず、自分が納得できる道を選びましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。